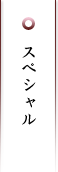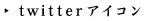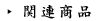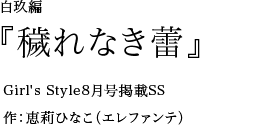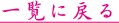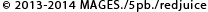いつからか、女形をやるようになってから、体を鍛えることが日課になっていた。
元々、目立って筋肉がつく体質ではないためか、女形姿になると一層細く見えるからだ。
別に、誰かにそんな風に言われたわけではないが、
こんな格好してるからといって、「体つきまで女みたいだ」なんて思われたら癪だ。
体を動かして汗をかくことは嫌いじゃないし、特に苦に思うことなく日々続けている。
今日もいつものように鍛錬を終え、体の汗を拭くために上半身だけ着物を脱ぐ。
手ぬぐいで身体を拭い始めたその時、ふいに障子の向こうから声がした。
「白玖さん、いらっしゃいますか?」
「七緒……?」
「はい。 失礼しますね」
「あ、ちょっと待っ……」
制止する間もなく、障子がすっと開かれる。
そのまま視界に入ってきた七緒の瞳が、俺を見て大きく見開かれた。
続いて、頬がみるみるうちに紅潮する。
「す、すみません……!! 失礼しましたっ!!」
「いや、別にいいけど……。見られて困るものでもないし」
この万珠屋で、たかが男の上半身裸を見たくらいでここまで初な反応をする娘は珍しい。
そう思い、試しについっと距離を詰めてみる。
「ほら、せっかくだからもっと近くで見てみる?」
「……っ……!?」
耳元でわざとらしく囁いてみると、七緒は息を呑み硬直した。
(……へぇ……この反応は……)
言うまでもないが、別に裸を見せる趣味があるわけじゃない。
けれど、こんな反応をされたら、からかいたくなるのが男の性だ。
「急に開けたってことは……俺の裸、見たかったんでしょ?」
「……ち、違います! 白玖さんのお返事がなかったので……!」
ややムキになって否定する七緒の視線は、決して俺に定まらない。
「ふぅん? 本当に……?」
「本当です! それより、は、早く着替えてください……!」
「くくく、はいはい。あんたは本当、反応が素直だから、飽きなくていいね」
俺は笑いながら、わざとなるべくゆっくり着物を整える。
「それで? 一体なんの用?」
「あ……」
そう問うと、七緒は思い出したように手に持っていた包みを広げた。
「あの……さっき大尽に、とてもいい羊羹をいただいたです。良かったら一緒にいかがですか?」
「は……? 羊羹?」
「はい」
「わざわざ、これを届けにきたの?」
「……? はい。白玖さん、最近お忙しそうでしたし……甘い物を食べると疲れが取れると思ったので」
何の疑いもなく屈託のない笑顔を見せる七緒に、俺は一瞬言葉を詰まらせる。
(……本当に、変わってる……)
俺はこの万珠屋で唯一の男の面方であり、
その上、この表情のせいなのか冷たい印象を与え、近寄りがたいとよく言われる。
禿や新造には遠巻きにされているのがほとんどで、
今の七緒のように、こうやって気軽に部屋を訪ねてくるような娘は万珠屋には存在しない。
(大体、この羊羹ってお上御用達の高級品だったと思うけど……)
これほど高級なものをもらったら、大抵の者は下に分け与えることはあっても、目上の者には持ってこないだろう。
少なくとも、自分ならそうだ。
そう考えながら、羊羹を一口つまむ。
「うん、美味しいね。さすが、お上御用達の羊羹ってだけはある」
「え? お上御用達って……この羊羹、そんなにいい羊羹なんですか?」
きょとんとした七緒の表情を見て、思わず苦笑する。
(これだけ上等な菓子をあげるってことは、相手の大尽は七緒に相当入れ込んでるってことになるけど……)
(この調子じゃ、そのことにもまったく気付いてないだろうね)
仮に、例えこの羊羹が上等なものだと知っていたとしても、七緒はきっと俺に分けに来るのだろう。
そういう気立てのある子だ。
そこまで考えて、ふと我に返る。
(……何ひとりで温かい気持ちになってるんだか)
柄にもない感情に居心地が悪くなり、別の話題を探して逡巡する。
「ここの暮らしには慣れた?」
そのまま咄嗟に浮かんだ質問を口にすると、七緒は大きな目で驚いたようにこちらを見る。
一拍置いて、自分でも愕然とする。
(……最悪。なんで、こんなこと……)
いくら適当な話題が欲しかったとはいえ、もっと他にあっただろう。
自分でも予想外の問いかけに戸惑っていると、不意に七緒がふわりと笑った。
「……はい、少しずつ慣れてきました」
その笑顔と、弾む声がやけに嬉しそうで――
何故か俺は、そのまま視線を逸らす。
「……ま、別にあんたが慣れていようがいまいが、どうでもいいんだけど」
次にした言葉は、いつも通りの憎まれ口だった。
突き放すように言ってしまったことを自覚し、ちらりと七緒を見てみる。
「初心忘れるべからず。慣れたからって、手を抜かないように」
「はい……!」
「……!」
一体何がそこまで嬉しいのか。 驚くことに七緒はにこにこと笑顔を崩さない。
そしてその汚れないまっすぐな笑顔が……
――なんだか、妙に気に入らなかった。
「この羊羹、本当に美味しいですね。白玖さん、羊羹もっと食べませんか?
このままだと私が全部食べてしまいそうです」
羊羹を一口に切り、爪楊枝を刺しながら七緒が言う。
「……そうだね。もらうよ」
「え? あ……っ!」
羊羹を口へ運ぼうとした七緒の細い手首を素早く掴み、強く引き寄せる。
そしてそのまま自分の口へと運んだ。
「は、白玖さん!?」
「こっちの方が、美味しそうに見えたから」
そう言ってまっすぐに七緒を見つめると、またもその頬が真っ赤に染まる。
耳まで赤くなっているのを見て、すっと胸がすいたのを感じる。
「わ、私の爪楊枝ですよ!?」
「だから?」
「い、嫌じゃないんですか……?」
「嫌? なんで?」
「……だ、だって白玖さん、そういうの気にされるじゃないですか」
「あんたのなら、別に気にならない」
「……っ!」
手を解放しながらそう答えると、七緒はそのまま視線を逸らして俯く。
(……ふ、今何を考えているのかが手に取るようにわかる)
可愛いもんだね、と心の中でそう呟いてハッとした。
(……可愛い? ……女を可愛いなんて思ったのはいつぶりだ……?)
(まさか、俺がこんなことを思うなんてな……)
(いや……違うな)
今日に限らず、七緒が万珠屋へ来てからはなんだか調子を狂わされっぱなしだ。
そう自覚し、思わず苦笑が漏れる。
「……参ったね」
「……? 白玖さん……?」
「なんでもない」
そう言ってひとつ咳払いをする。
俺が今、何を思っているのかなんて、絶対に教えない。
(……きっと、色恋沙汰ってこういうなんでもないところから始まるものなんだろうな)
ふと、どこか他人事のように考えながら俺は頬杖をつく。
目の前では、いまだに七緒が爪楊枝をそのまま使うべきか悩んでいるように見えた。
頬もまだ赤く染まったままだ。
(……ほんと、無垢で愛らしい子だね)
(でも無垢すぎて……なんだか汚したくなる)
そんな思いが脳裏を掠め、俺は七緒から目を逸らし窓の外へと視線を移す。
――まさか、後に自分が七緒に溺れることになるなんて
誰にも触れさせたくないと思うほど、恋焦がれる相手になるなんて……――
当然、この時の俺は知る由もなかった。
了