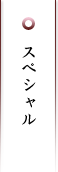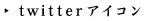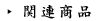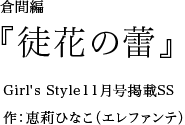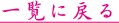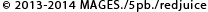秋晴れの、気持ちのいい昼下がりのこと。
僕は七緒ちゃんと二人、鷲大明神社へやって来た。
今日はここで酉の市が開催されている。
「凄い人出ですね……」
目を輝かせて神社に足を踏み入れた七緒ちゃんが、人混みを見て怯んでいる。
「毎年、迷子が出て大変みたいだよ」
そう言うと、深く感じ入ったように七緒ちゃんは頷いた。
多分、ここではぐれたらどうしようとか、そんなことを考えているのだと思う。
「だから、はぐれないようにしないとね」
できるだけ軽い口調で言って、彼女の手を握る。
「……え」
戸惑った声には気づかないふりをして、僕はそのまま歩を進める。
「熊手を買うんだっけ?」
「は、はい。万珠屋に飾るんだそうです」
「どれくらいの大きさがいい?」
手を繋いでいることに意識を集中させすぎないよう、質問を重ねながら歩いた。
握った手の平は小さく、僕よりも幾らか高い熱を放っている。
「七緒ちゃんは、江戸に来たばかりの頃と比べると見違えるように変わったよね」
「え……そうですか?」
「うん。中身というより雰囲気かな? すっかり江戸に慣れたようだし、なんだか綺麗になった」
「そんなことないですよ」
思ったままを口にすると七緒ちゃんは慌てたように謙遜した。
本心から思っていることなのに、素直に褒めると彼女は困ったような顔をする。
「そんなことあるよ。七緒ちゃんのことが眩しくて、前より直視できなくなってるんだから」
「ふふ、なんですかそれ」
少し大袈裟な言い方をしてみせると、七緒ちゃんは楽しげに笑った。
(……全部、本当のことなんだけどね)
少なくとも、僕の目にはそう映っている。
七緒ちゃんは綺麗になったし、愛らしいし、誰もに好かれるような子だと思う。
だから……
(僕はこれからも、こんな風になんでもない振りをすることでしか、君に触れることが出来ない)
なんてことのないように手を握ったり、大袈裟なくらいの賛辞を繰り返していけば
彼女はきっと、こういう僕に慣れていってくれるだろう。
(そうしたらまた次も、こうやって自然に君と歩くことができる)
僕なりのスキンシップだと、七緒ちゃんが思ってくれればそれでいい。
触れたいと思った時に触れられる距離を、我慢したいとは思わない。
(でも、これじゃ君の心の中には入れないんだろうけど……)
それでもいい。
否、それが一番いいと自分に言い聞かせる。
本心は全て胸に秘め続けて、僕は一生“君の味方”で居続ける。
(……本気だと思ってもらえないのは、案外寂しいものなんだけどね)
矛盾した自分の思考に苦笑しつつ、隣の七緒ちゃんにそっと視線を送る。
握ったばかりの時は緊張していた手が、今は自然に僕と繋がっていた。
「これからも、君はどんどん綺麗になっていくんだろうな」
「え……?」
「……嬉しいような、寂しいような、複雑な気分だな」
「寂しい……?」
「んー、こっちの話」
そう答えると、七緒ちゃんはそれ以上追求してこなかった。
それから、なんとなく話題が途切れてしまう。
けれど沈黙は悪いものではなく、祭囃子の音色や人々の笑い声が、僕たちを賑やかに包んでいた。
(……あ、熊手だ)
しばらくして、目的の物が置いてある屋台を見つけたので彼女に声をかける。
「七緒ちゃん」
「…………」
返ってこない反応にもう一度声を掛ける。
「七緒ちゃん?」
「えっ……あ、すみません」
ぼんやりしていたらしく、ハッとしたように視線がこちらへ向く。
何を見ていたのか気になり視線の先を辿り――合点がいった。
視線の先にあったのは人混みの中にいる祖父と孫が微笑ましげに歩いているものだったり、
仲の良さそうな友人同士が楽しげに屋台を眺めているものだったり……
(……やっぱり、寂しいんだろうな)
七緒ちゃんの境遇を思うと、胸が痛んだ。
彼女は、万珠屋の面方としてよく頑張っていると思う。
だけど馴染みのないこの江戸で、果たして心を許せる相手はいるのだろうか。
家族も友人もいない中、七緒ちゃんの心の拠り所はどこにあるのか。
「ちょっと、あれやっていかない?」
ふと目に付いた屋台に、僕は彼女の手を引いて立ち寄った。
大きな桶の中でひらひらと舞う赤い金魚を見て、彼女の顔がぱっと華やぐ。
「親父さん、一回」
銅銭を金魚屋に手渡し、掬い網とお椀を受け取る。
「七緒ちゃん、気になる金魚はいる?」
「そうですね……あっ、その子がいいです」
指し示されたのは、群れからはぐれたように桶の隅を一匹で泳ぐ、小さな金魚だった。
僕はそれを、できるだけそっと網で掬う。
「はい。これは君の金魚だよ」
「いいんですか?」
「うん」
お椀に入れた金魚を渡すと、七緒ちゃんは嬉しそうに受け取った。
(この金魚が、少しでも君の心の慰めになるといいけれど)
――不意に、記憶の中で昔に聞いた言葉が思い起こされた。
狭い世界の中で着飾り、優雅に泳ぐ金魚は、まるで遊女のようだと。
寂しげな笑みと共に零された台詞が、とても哀しく響いたのを思い出す。
(……七緒ちゃんには、そんな思いをさせたくない)
(この子は、幸せにしてあげたい。……絶対に)
僕には、七緒ちゃんが幸せになるのを見届ける義務がある。
この子を幸せにする役目は僕ではないけれど、見届ける役目は絶対に誰にも渡さない。
(だから、君を守ってくれる相手が見つかるまでは……せめて、こうして一番近くにいられますように)
どれだけ強く願ったところで、願いが成就するわけではないと知っているけれど……
それでも、願わずにはいられない。
「ありがとうございます。大切に育てますね」
僕を真っ直ぐに見て七緒ちゃんが言う。
その瞳に滲んだ微かな涙は、寂しさから来るものだろうか。
嬉し涙だったらいいと思いながらも、僕はそっと視線を逸らす。
(この子は、見かけによらず強い子だから)
寂しさや不安を表に出すことはほとんどない。
涙に気付かれることも、きっと嫌がるだろう。
言葉を尽くして慰められることを良しとしない強さを、僕は美しいと思う。
けれど、それと同時に強く思う。
――この子から決して目を離してはいけない、と。
「それじゃ、最後に熊手を買って帰ろうか?」
「はい」
頷いた七緒ちゃんの目には、まだ涙が光っていたけれど……。
僕は何も言わずに彼女の手を取った。
(……願わくば)
このひとときが、少しでも長く続きますように――
了